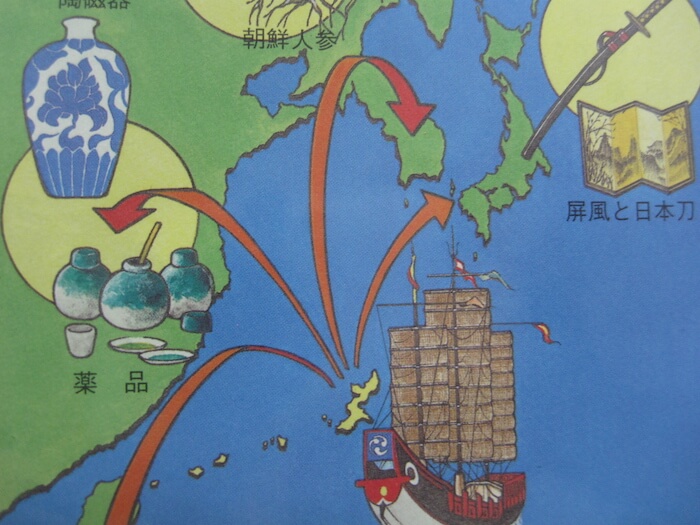 いなぐ・いきー
いなぐ・いきー 琉球王国は、どのようにして生まれたのか?
一三六八年(足利義満、十一才で征夷大将軍即位)中国には「明」という漢民族の王朝が誕生します。その前の「元王朝」は北方民族のモンゴル人が作った国で約百年間続いていました。中国は、北方民族と中央の漢民族のあいだでくりかえされた、果てしない戦いの...
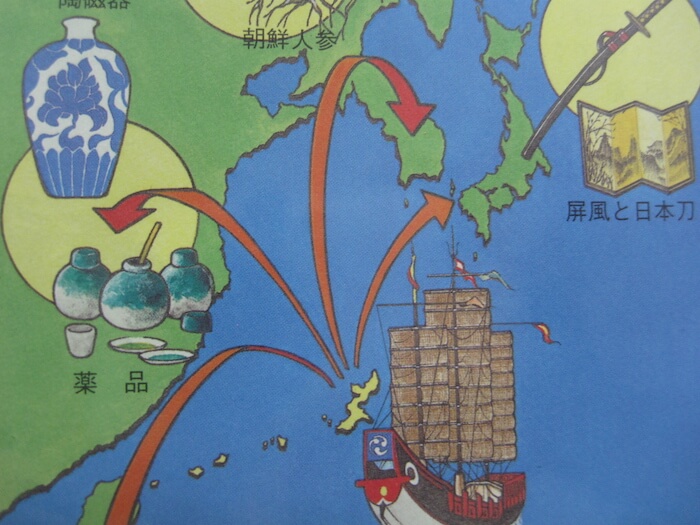 いなぐ・いきー
いなぐ・いきー 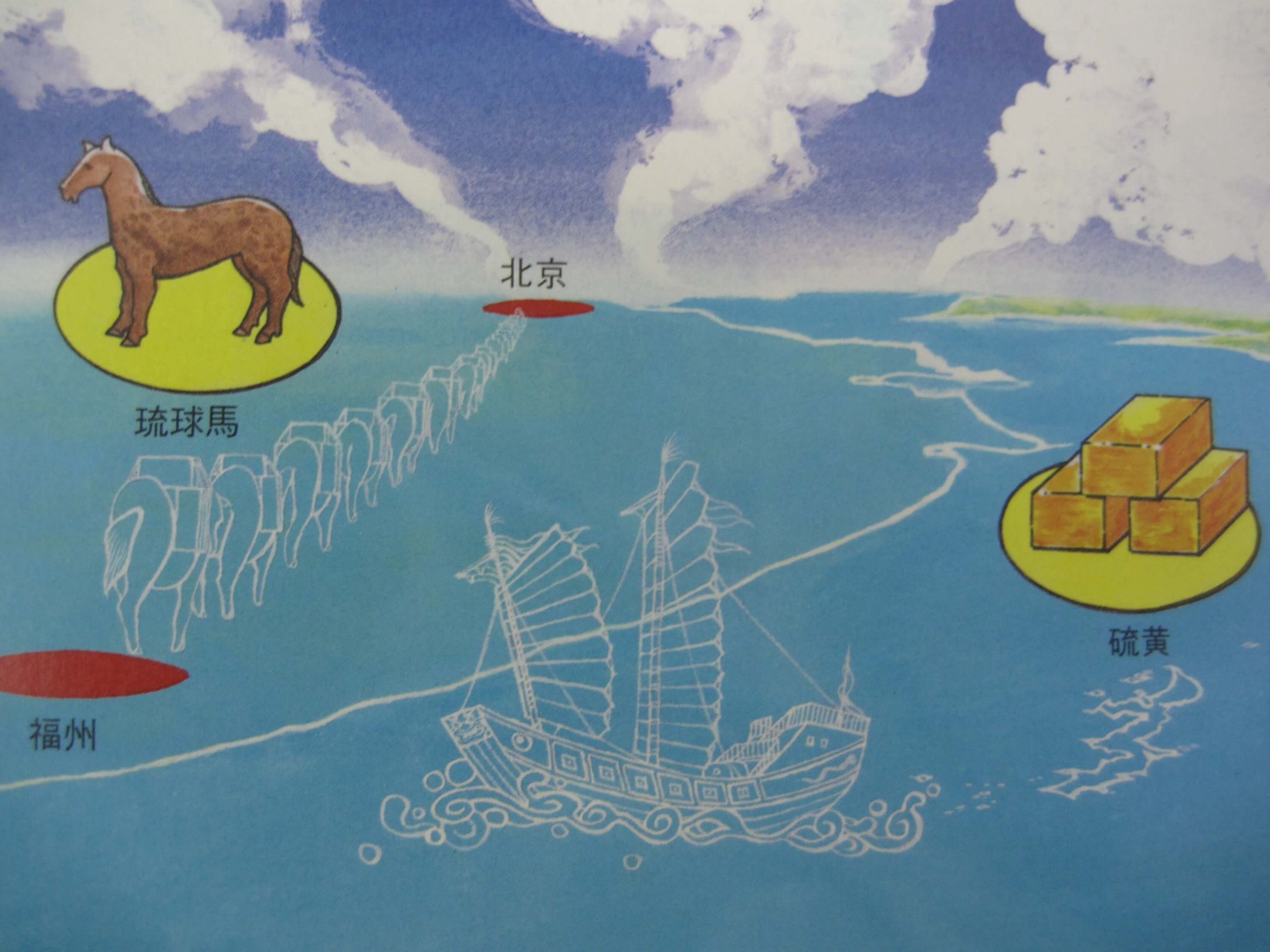 いなぐ・いきー
いなぐ・いきー 」.jpg) いなぐ・いきー
いなぐ・いきー